前の3件 | -
短歌、俳句、冬~春(2023年11月下旬~4月中旬くらい) [その他]
燗酒を啜る背中に熊手買う拍子木の音刺さる夕暮れ
霜月の上野の山の夕暮れを黒一閃に割く大烏
立つ湯気に浮かぶまだ見ぬ家族かな
茶葉買えぬ家に白湯沸く侘び師走
望みなき師走の午後よ長閑なり
恥を背負い生き長らえた足跡よ師走の雨に溶けて流れよ
吐く息の白きは魂か今朝の生
隅田川照らす灯りに星の降るアルルよぎれば帰りの車窓
背中押す師走の風の冷たさは清く厳しい師の声に似て
死に損ねまた蕎麦香る大晦日
元旦に白湯温かし生きよ皆
翼無く命綱無く果てし無く虚空を落ちよ刻至るまで
成人の日を振り返る老い支度
独り寝に心凍てつく寒さにも残躯蝕む熱の火照りは
白湯啜り己の冬を生き延びよ
待ちわびた姿おぼろに寒い夜
芯までかじかんた指で文字を打ち君の返事のぬくもりを待つ
脳髄にハリガネムシを飼うごとく鈍き水面に身投げ思えど
傘の無い我が身を射るや冬の雨
雨の夜に会いたい人の面影が思いの底に揺らぎかそけし
うなだれて吐くため息の白き朝
白湯に溶く醤油に暖の春まだき
生きる気持ちは心から枯れ果てても髪と爪とが伸びる我が身は
如月の雨をたくわえ香る土
稲妻が裂く雪の夜の裁きかな
世の中はとてもかくても膿爛れサルダナパールの鼻は崩れぬ
積もる雪融かすや祈る経の声
街角に冬のほどける風優し
黎明に冬討つ風の凄まじき
春雨の闇にカレーの香りかな
ぬるまった燗を惜しめば名残酒
雨寒し抗う冬の涙かな
燗酒の湯気を透かして恋心
暁に覚めれば白きなごり雪
逝く春や平成遠くなりにけり
ひねもすの春雨に酔うつぼみかな
花散るや風凄まじき朝ぼらけ
凍てついた風に射られて彼岸かな
泣けるまで大蒜まぶせ初鰹
花冷えの闇に震えて沸かす白湯
夜桜の知られずに散る思いかな
花冷えが凍みて目覚める午前四時
君と僕。いつか必ず死ぬことがただ一つだけの近しいところ。
花冷えに抱かれ闇に咳一つ
霜月の上野の山の夕暮れを黒一閃に割く大烏
立つ湯気に浮かぶまだ見ぬ家族かな
茶葉買えぬ家に白湯沸く侘び師走
望みなき師走の午後よ長閑なり
恥を背負い生き長らえた足跡よ師走の雨に溶けて流れよ
吐く息の白きは魂か今朝の生
隅田川照らす灯りに星の降るアルルよぎれば帰りの車窓
背中押す師走の風の冷たさは清く厳しい師の声に似て
死に損ねまた蕎麦香る大晦日
元旦に白湯温かし生きよ皆
翼無く命綱無く果てし無く虚空を落ちよ刻至るまで
成人の日を振り返る老い支度
独り寝に心凍てつく寒さにも残躯蝕む熱の火照りは
白湯啜り己の冬を生き延びよ
待ちわびた姿おぼろに寒い夜
芯までかじかんた指で文字を打ち君の返事のぬくもりを待つ
脳髄にハリガネムシを飼うごとく鈍き水面に身投げ思えど
傘の無い我が身を射るや冬の雨
雨の夜に会いたい人の面影が思いの底に揺らぎかそけし
うなだれて吐くため息の白き朝
白湯に溶く醤油に暖の春まだき
生きる気持ちは心から枯れ果てても髪と爪とが伸びる我が身は
如月の雨をたくわえ香る土
稲妻が裂く雪の夜の裁きかな
世の中はとてもかくても膿爛れサルダナパールの鼻は崩れぬ
積もる雪融かすや祈る経の声
街角に冬のほどける風優し
黎明に冬討つ風の凄まじき
春雨の闇にカレーの香りかな
ぬるまった燗を惜しめば名残酒
雨寒し抗う冬の涙かな
燗酒の湯気を透かして恋心
暁に覚めれば白きなごり雪
逝く春や平成遠くなりにけり
ひねもすの春雨に酔うつぼみかな
花散るや風凄まじき朝ぼらけ
凍てついた風に射られて彼岸かな
泣けるまで大蒜まぶせ初鰹
花冷えの闇に震えて沸かす白湯
夜桜の知られずに散る思いかな
花冷えが凍みて目覚める午前四時
君と僕。いつか必ず死ぬことがただ一つだけの近しいところ。
花冷えに抱かれ闇に咳一つ
子瑜漠々~諸葛兄弟異聞~ [フィクション]
秋風とともに入ってきた、弟の訃報。複数の情報筋を照合したところ、それは疑いえない事実であった。弟の死を知らせる文書類を机上に、私は、しばし目を瞑る。いつも思い出す、子供の頃、あの日の川。そして、弟の横顔。
その川に流れは無かった。青緑色をしていたはずの水は、ほとんど川下へ流れることもなく赤黒く染まり、池のような沼地のような水溜まりをなしている。水溜まりを堰き止めているのは、数え切れぬほどの死体だ。
老人、子供、男、女、兵、農民…ある者は頭を砕かれ、ある者は腹を裂かれ、ある者は首を切られ、ある者は手足を失い、とりどりの死体が川を堰き止めている。
その異様な水溜まりを尻目に、まだ子供だった私は、すぐ下の弟の手を取り、はぐれた両親や家族を探しに彷徨い歩いている。家族と合流しなければ、早晩、自分も弟も、川を堰き止めている死体たちの仲間に入るだろう。せめて、弟だけでも。聞き分けがよく、こんな状況でも泣き言一つ言わない弟。
どうにかして、この子を連れ帰らねば。
歩きつつ、濃厚な死者の臭いが混じる風に、ほんの少し、違うものが混じる。砂煙。風上を見ると馬に乗った人の集団。兵隊だ。身を隠そうと、弟の手を取り、少し先の草むらまで走ろうと試みる。だが、いくら手を引っ張っても弟の身体は動かない。
「亮?亮?」
砂埃から、少しずつ人の形が現れてくる。やはり、馬に乗った兵隊たち。見つかったらどんな目に合うかわからない。うっすらと旗印も見えてきた。だが弟の目は遠くの旗印を見据え、身体はまるで根っこでも生えたように動かない。
「亮、亮!」弟の身体を揺さぶる。そんな私の声や思いを知ってか知らずか、
「曹…操…」目を細めて旗印を読む弟。
その後幾十年にもわたり、宮廷や戦場で、英雄や豪傑や名士と呼ばれる多くの人々と渡り合ってきた私だが、このときの弟ほど、冷たく、そして暗く沈んだ怒りに満ち満ちた表情の人物を見たことが無い。そんな弟が急逝したとの報が、立て続けに私の下に舞い込んできたのである。
蜀漢帝国丞相、諸葛亮、字は孔明。私の弟の今の呼び名だ。だが今の私には、徐州のあの川のほとりが脳裏から離れない。
あの川を這う這うの体で離れ、弟と私含めた家族は、曹操軍による殺戮をどうにか逃れることができた。中原の戦乱から逃れるため、私は、母を連れて、孫策どのが勢力を築きつつあった江東に遊学しながら仕官の機を窺うことに決めた。弟たちは荊州の親類に託されることとなった。
華北では、曹操が袁紹を破って中華の覇権を握ろうとしつつあるころ、江東では、暗殺で非業の死を遂げた孫策どのの跡を、陛下、つまり孫権どのが継いだばかり。そんな孫権どのに、私は仕えることになった。
数年ほどの勤務を経て孫権どのの信頼を得つつあった私は、弟を江東に招こうと考えた。預けた荊州の親類はすでに亡く、幼いころから才知に恵まれた弟なら、孫権どのの役にも立つはずだ。母も喜ぶに違いない。しかし、手紙にこそ返事はあるものの、江東に来ることに関しては、色よい返事が無かった。弟が妻を娶ったことも、手紙で知った。
あるとき、孫権どのの命で、荊州へ使いすることが決まる。この機会に、弟に会ってみよう、そう思い手紙を出しておいた。
荊州についた私は、それとなく弟の消息を訪ねた。幸いなことに、弟の嫁は土地の名士、黄承彦の娘であり、そのおかげもあってか、弟の暮らしにそれほど不自由も無いことがわかって安心する。現地の名士たちの間にも出入りしている弟は、一部では、「伏龍」「臥龍」ともあだ名されているそうだ。
弟の家は、すぐに見つかる。何の変哲もない農夫の家。傍の畑で汗だくになって草取りをしている大柄の男、身体こそ大きくなったが、見間違いようが無い。弟だ。たまらず、声をかける。
「兄さん、そろそろ、おいでになる頃と思ってました」
そう返事をし、汗をぬぐう弟の、浅黒い、莞爾とした顔からは、戦の続く中原や江東の民には見られぬ健やかさがあった。さっそく、弟の家に招かれる。その妻にも紹介してもらった。しばし、二人で差し向かいで話す。子供の頃の話、お互いの、荊州や江東での話。古今の人物の話。話題は尽きない。
自然、今の人物の話になる。弟は、どこから情報を仕入れているのか、荊州だけでなく、中原や益州、西涼の人物にもそれなりの関心と知見を持っているようだ。曹操はもちろん、すでに亡き袁紹、劉表、劉璋、馬騰等々。その意見は、参考になることも少なくない。私がそのことを褒めると、
「いや、中原から逃れてきた人々が、それとなく教えてくれるだけです」
と、かぶりを振る。ますます、孫権どのの下で一緒に働いてみたくなる。
会話の中でそれとなく、孫権どのの話を織り交ぜてみることにする。若くして孫策どのの跡を継ぎ、群臣たちの心を掴んだその立ち居振る舞い、張昭どのや周瑜どのをはじめとする群臣たちの優秀さ、その若さと気力。もちろん、褒めるだけではいけない。その稚気や幼さなど、直していただくべきところも触れる。弟の顔がふっと綻ぶ。私も釣られて微笑む。
今だ。
孫権どのへの仕官を持ちかける。弟は一瞬目を見開き、そして瞑った。ずいぶんと長く感じた沈黙だが、ほんの数刻だったのかもしれない。次に目を開いたとき、弟は併せて口も開く。
「孫権どのは、確かに、一世の英雄でしょう。しかし、孫権どのには」
能弁だった弟が、まるで言葉を探すかのように口ごもる。
「孫権どのには」
そして、こう絞り出した。
「思いが、足りぬのです」
弟の顔には、幼いころ徐州のあの川のほとりで見たあのときの表情が刻まれていた。私は、仕官の説得を諦めた。ただ、弟の心の芯に触れた気がして、説得の失敗も、どこか喜ばしいような、そんな気持ちを抑えきれなかった。その日は夜が明けるまで飲んで、話して、笑い合い、二人してしたたかに酔ったのを、今なお覚えている。
それから、外交の使者として弟と意見を交換することこそ何度かあったが、二人きりで腹を割って話すのは、あのときが最後となった。
数年経た劉表の死後、そこに寄寓していた左将軍劉備の招聘を受け入れ、弟は、その軍師として活躍を見せる。劉備が弟をどのように説得したのかは詳しくはわからない。ただ、歴戦の豪傑である古参の武将、関羽や張飛をも上回る寵遇が江東の私の耳にも伝わるほどだった。魯粛どのの手引きで同盟の使者として来訪した弟を引見した孫権どのからは、弟の懐柔を命ぜられたが、私は不可能としてお断りした。
そして、赤壁の戦、荊州争奪、劉備の蜀獲り、関羽征伐、劉備の即位、宜都の役、劉備の死。
孫権どのに無く、劉備には在った思い。おそらくはその思いのために、丞相としての弟は、曹魏への北伐に邁進する。間者から折々に知らされるその緻密にして大胆な作戦は、呉の大将軍を拝命した私を唸らせるのに十分だった。しかし、北伐は志半ばで潰えた。
もちろん、蜀と魏の国力差は歴然としていており、試みそのものが無茶だったとも言える。それに加え、語弊を恐れずに言えば、蜀漢には、弟ただ一人しかいなかったこともあるだろう。
それが、蜀漢の人材不足にあったのか、弟の人材育成の不備だったのか、もしくはその両方だったのかつまびらかではない。だが、政務の上では丞相の顧雍どの。軍事においては上大将軍の陸遜どのと、憚りながら大将軍たる私をはじめ、戦線を任せられる将軍が何人かいる我が孫呉と比べれば、弟の双肩にかかる負担が大きかったのは間違いない。
弟も、確か五十歳は超えていたはずだ。六十歳を超えた私よりも若いが、世の常として、早すぎるとは言えない。徐州のあの川のほとりでの思いとともに、弟は、燃え尽きたのだろうか。
弟亡き蜀漢がどうなるのか、予断は許さない。しかし、弟の残した遺徳は、まだしばらく神通力を保つことだろう。我が呉として、軽挙妄動する必要は無い。
気が付くと、家の者が灯火をつけてくれており、夜半を回っていた。弟、いや、諸葛亮死後における蜀への対処方針案につき、孫権どの、いや陛下に奏上する一通り文書の草稿を書き終えると、外の空気を吸いたくなった。秋風に身が震える。弟が息を引き取った北方、五丈原は、さらに寒かったことだろう。
夜空は晴れ、瞬いているはずの星々は、どこかしらおぼろげに霞んでいる。目尻から頬に、涙が伝った。涙を拭い、少しだけはっきりとした星空に、赤黒く輝く、ひときわ大きな星が見えた。ほんの数刻揺らめくやいなや、その星は、軌跡を描いて西方に墜ちていった。
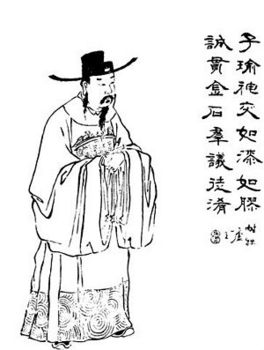
その川に流れは無かった。青緑色をしていたはずの水は、ほとんど川下へ流れることもなく赤黒く染まり、池のような沼地のような水溜まりをなしている。水溜まりを堰き止めているのは、数え切れぬほどの死体だ。
老人、子供、男、女、兵、農民…ある者は頭を砕かれ、ある者は腹を裂かれ、ある者は首を切られ、ある者は手足を失い、とりどりの死体が川を堰き止めている。
その異様な水溜まりを尻目に、まだ子供だった私は、すぐ下の弟の手を取り、はぐれた両親や家族を探しに彷徨い歩いている。家族と合流しなければ、早晩、自分も弟も、川を堰き止めている死体たちの仲間に入るだろう。せめて、弟だけでも。聞き分けがよく、こんな状況でも泣き言一つ言わない弟。
どうにかして、この子を連れ帰らねば。
歩きつつ、濃厚な死者の臭いが混じる風に、ほんの少し、違うものが混じる。砂煙。風上を見ると馬に乗った人の集団。兵隊だ。身を隠そうと、弟の手を取り、少し先の草むらまで走ろうと試みる。だが、いくら手を引っ張っても弟の身体は動かない。
「亮?亮?」
砂埃から、少しずつ人の形が現れてくる。やはり、馬に乗った兵隊たち。見つかったらどんな目に合うかわからない。うっすらと旗印も見えてきた。だが弟の目は遠くの旗印を見据え、身体はまるで根っこでも生えたように動かない。
「亮、亮!」弟の身体を揺さぶる。そんな私の声や思いを知ってか知らずか、
「曹…操…」目を細めて旗印を読む弟。
その後幾十年にもわたり、宮廷や戦場で、英雄や豪傑や名士と呼ばれる多くの人々と渡り合ってきた私だが、このときの弟ほど、冷たく、そして暗く沈んだ怒りに満ち満ちた表情の人物を見たことが無い。そんな弟が急逝したとの報が、立て続けに私の下に舞い込んできたのである。
蜀漢帝国丞相、諸葛亮、字は孔明。私の弟の今の呼び名だ。だが今の私には、徐州のあの川のほとりが脳裏から離れない。
あの川を這う這うの体で離れ、弟と私含めた家族は、曹操軍による殺戮をどうにか逃れることができた。中原の戦乱から逃れるため、私は、母を連れて、孫策どのが勢力を築きつつあった江東に遊学しながら仕官の機を窺うことに決めた。弟たちは荊州の親類に託されることとなった。
華北では、曹操が袁紹を破って中華の覇権を握ろうとしつつあるころ、江東では、暗殺で非業の死を遂げた孫策どのの跡を、陛下、つまり孫権どのが継いだばかり。そんな孫権どのに、私は仕えることになった。
数年ほどの勤務を経て孫権どのの信頼を得つつあった私は、弟を江東に招こうと考えた。預けた荊州の親類はすでに亡く、幼いころから才知に恵まれた弟なら、孫権どのの役にも立つはずだ。母も喜ぶに違いない。しかし、手紙にこそ返事はあるものの、江東に来ることに関しては、色よい返事が無かった。弟が妻を娶ったことも、手紙で知った。
あるとき、孫権どのの命で、荊州へ使いすることが決まる。この機会に、弟に会ってみよう、そう思い手紙を出しておいた。
荊州についた私は、それとなく弟の消息を訪ねた。幸いなことに、弟の嫁は土地の名士、黄承彦の娘であり、そのおかげもあってか、弟の暮らしにそれほど不自由も無いことがわかって安心する。現地の名士たちの間にも出入りしている弟は、一部では、「伏龍」「臥龍」ともあだ名されているそうだ。
弟の家は、すぐに見つかる。何の変哲もない農夫の家。傍の畑で汗だくになって草取りをしている大柄の男、身体こそ大きくなったが、見間違いようが無い。弟だ。たまらず、声をかける。
「兄さん、そろそろ、おいでになる頃と思ってました」
そう返事をし、汗をぬぐう弟の、浅黒い、莞爾とした顔からは、戦の続く中原や江東の民には見られぬ健やかさがあった。さっそく、弟の家に招かれる。その妻にも紹介してもらった。しばし、二人で差し向かいで話す。子供の頃の話、お互いの、荊州や江東での話。古今の人物の話。話題は尽きない。
自然、今の人物の話になる。弟は、どこから情報を仕入れているのか、荊州だけでなく、中原や益州、西涼の人物にもそれなりの関心と知見を持っているようだ。曹操はもちろん、すでに亡き袁紹、劉表、劉璋、馬騰等々。その意見は、参考になることも少なくない。私がそのことを褒めると、
「いや、中原から逃れてきた人々が、それとなく教えてくれるだけです」
と、かぶりを振る。ますます、孫権どのの下で一緒に働いてみたくなる。
会話の中でそれとなく、孫権どのの話を織り交ぜてみることにする。若くして孫策どのの跡を継ぎ、群臣たちの心を掴んだその立ち居振る舞い、張昭どのや周瑜どのをはじめとする群臣たちの優秀さ、その若さと気力。もちろん、褒めるだけではいけない。その稚気や幼さなど、直していただくべきところも触れる。弟の顔がふっと綻ぶ。私も釣られて微笑む。
今だ。
孫権どのへの仕官を持ちかける。弟は一瞬目を見開き、そして瞑った。ずいぶんと長く感じた沈黙だが、ほんの数刻だったのかもしれない。次に目を開いたとき、弟は併せて口も開く。
「孫権どのは、確かに、一世の英雄でしょう。しかし、孫権どのには」
能弁だった弟が、まるで言葉を探すかのように口ごもる。
「孫権どのには」
そして、こう絞り出した。
「思いが、足りぬのです」
弟の顔には、幼いころ徐州のあの川のほとりで見たあのときの表情が刻まれていた。私は、仕官の説得を諦めた。ただ、弟の心の芯に触れた気がして、説得の失敗も、どこか喜ばしいような、そんな気持ちを抑えきれなかった。その日は夜が明けるまで飲んで、話して、笑い合い、二人してしたたかに酔ったのを、今なお覚えている。
それから、外交の使者として弟と意見を交換することこそ何度かあったが、二人きりで腹を割って話すのは、あのときが最後となった。
数年経た劉表の死後、そこに寄寓していた左将軍劉備の招聘を受け入れ、弟は、その軍師として活躍を見せる。劉備が弟をどのように説得したのかは詳しくはわからない。ただ、歴戦の豪傑である古参の武将、関羽や張飛をも上回る寵遇が江東の私の耳にも伝わるほどだった。魯粛どのの手引きで同盟の使者として来訪した弟を引見した孫権どのからは、弟の懐柔を命ぜられたが、私は不可能としてお断りした。
そして、赤壁の戦、荊州争奪、劉備の蜀獲り、関羽征伐、劉備の即位、宜都の役、劉備の死。
孫権どのに無く、劉備には在った思い。おそらくはその思いのために、丞相としての弟は、曹魏への北伐に邁進する。間者から折々に知らされるその緻密にして大胆な作戦は、呉の大将軍を拝命した私を唸らせるのに十分だった。しかし、北伐は志半ばで潰えた。
もちろん、蜀と魏の国力差は歴然としていており、試みそのものが無茶だったとも言える。それに加え、語弊を恐れずに言えば、蜀漢には、弟ただ一人しかいなかったこともあるだろう。
それが、蜀漢の人材不足にあったのか、弟の人材育成の不備だったのか、もしくはその両方だったのかつまびらかではない。だが、政務の上では丞相の顧雍どの。軍事においては上大将軍の陸遜どのと、憚りながら大将軍たる私をはじめ、戦線を任せられる将軍が何人かいる我が孫呉と比べれば、弟の双肩にかかる負担が大きかったのは間違いない。
弟も、確か五十歳は超えていたはずだ。六十歳を超えた私よりも若いが、世の常として、早すぎるとは言えない。徐州のあの川のほとりでの思いとともに、弟は、燃え尽きたのだろうか。
弟亡き蜀漢がどうなるのか、予断は許さない。しかし、弟の残した遺徳は、まだしばらく神通力を保つことだろう。我が呉として、軽挙妄動する必要は無い。
気が付くと、家の者が灯火をつけてくれており、夜半を回っていた。弟、いや、諸葛亮死後における蜀への対処方針案につき、孫権どの、いや陛下に奏上する一通り文書の草稿を書き終えると、外の空気を吸いたくなった。秋風に身が震える。弟が息を引き取った北方、五丈原は、さらに寒かったことだろう。
夜空は晴れ、瞬いているはずの星々は、どこかしらおぼろげに霞んでいる。目尻から頬に、涙が伝った。涙を拭い、少しだけはっきりとした星空に、赤黒く輝く、ひときわ大きな星が見えた。ほんの数刻揺らめくやいなや、その星は、軌跡を描いて西方に墜ちていった。
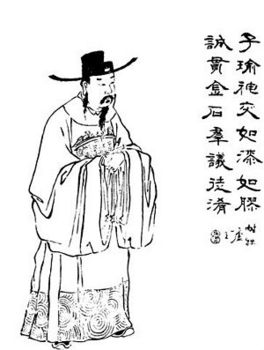
『ドラゴンクエスト』~鳥山明先生、どうか安らかに。。。~ [その他]
鳥山明氏が亡くなった。
『ドラゴンボール』はじめ数々のマンガの名作で、日本のみならず海外でも知られた鳥山氏だが、自分としては、1986年発売のファミコンゲーム、『ドラゴンクエスト』のキャラクターデザインが、今でも心に刻まれている。
スライム、ドラキー、ゴースト、おおさそり、まほうつかい、がいこつ、リカント、キメラ、よろいのきし、ドロル、ゴーレム、ドラゴン、そして、りゅうおう、、、
怖さやグロテスクさもありながら、どこか愛嬌があって憎めないモンスターの数々。当時、剣と魔法もののファンタジーの絵は、海外のイラストレーターか、その影響を強く受けたいかついものが多く、子供心に取っ付きにくかった。そのため、『ドラゴンクエスト』のモンスターたちのファンシーさには即座に惹き付けられたのである。
もちろん、『ドラゴンクエスト』は、当時の子供たちにとって、シナリオもゲーム性も全くもって新しかった。「にじのしずく」を手に入れるための謎解き。洞窟の中の「ローラひめ」の救出と「さくやはおたのしみでしたね」。結構泣かされた「ふっかつのじゅもん」の書き写し間違い。何度も挑んでは敗れるりゅうおうとの闘い。
ゲームと言えばアクションやシューティングが主だった時代に、RPGがまさに燦然と現れたのである。その衝撃は未だに覚えている。ちなみに当時、親にねだり続けてようやくファミコンソフトを買ってもらえる機会が生じ、『魔界村』と『ドラゴンクエスト』のいずれかの選択を迫られたが、『ドラゴンクエスト』を選んで心底よかったと、今でも思う。
周知のとおり、『ドラゴンクエスト』はその後、『ドラゴンクエスト2 悪霊の神々』『ドラゴンクエスト3 そして伝説へ』と続き、僕ら当時の子供たちの脳を焼きながらシリーズを続け、大人となった僕らをも魅了し続けている。
その意味では、子供心の『ドラゴンクエスト』と鳥山明氏のキャラクターデザインは、日本人のファンタジー観やRPG観を築いた源泉の一つと言っても、過言ではないだろう。その影響は、もはや潜在意識に刷り込まれており、抽出するのが難しいとすら言えるのではないか。
さて、僕らが生きてる現実には、教会も、ザオラルもザオリクも無い。死んだ人が生き返ることは無いのである。しかし、鳥山明氏が生み出した作品は、今、世界各国で生きている人々の心の中に生きているし、それに心動かされた人々が、更なる思い出や物語や作品を紡いでいくことになるのは確実だ。
様々な国の人々に楽しみを与え、人の心を動かし、新たな作品を生む原動力となったであろう鳥山明氏の業績は果てしない。
なまじな外交会議や経済支援よりも、鳥山明作品の方が、海外の人々の架け橋になっていることもあろう。また、人類への影響力として、後世、釈迦やソクラテスや孔子やキリストやムハンマドと並べて語られるのではなかろうか。なんて思ってみたりもする。
ともあれ、鳥山明先生の作品はもう見られない。それは確かに寂しいことには違いない。せめて、残された作品をきちんと愛することにしよう。どうか、安らかに。
.jpg) が
が
『ドラゴンボール』はじめ数々のマンガの名作で、日本のみならず海外でも知られた鳥山氏だが、自分としては、1986年発売のファミコンゲーム、『ドラゴンクエスト』のキャラクターデザインが、今でも心に刻まれている。
スライム、ドラキー、ゴースト、おおさそり、まほうつかい、がいこつ、リカント、キメラ、よろいのきし、ドロル、ゴーレム、ドラゴン、そして、りゅうおう、、、
怖さやグロテスクさもありながら、どこか愛嬌があって憎めないモンスターの数々。当時、剣と魔法もののファンタジーの絵は、海外のイラストレーターか、その影響を強く受けたいかついものが多く、子供心に取っ付きにくかった。そのため、『ドラゴンクエスト』のモンスターたちのファンシーさには即座に惹き付けられたのである。
もちろん、『ドラゴンクエスト』は、当時の子供たちにとって、シナリオもゲーム性も全くもって新しかった。「にじのしずく」を手に入れるための謎解き。洞窟の中の「ローラひめ」の救出と「さくやはおたのしみでしたね」。結構泣かされた「ふっかつのじゅもん」の書き写し間違い。何度も挑んでは敗れるりゅうおうとの闘い。
ゲームと言えばアクションやシューティングが主だった時代に、RPGがまさに燦然と現れたのである。その衝撃は未だに覚えている。ちなみに当時、親にねだり続けてようやくファミコンソフトを買ってもらえる機会が生じ、『魔界村』と『ドラゴンクエスト』のいずれかの選択を迫られたが、『ドラゴンクエスト』を選んで心底よかったと、今でも思う。
周知のとおり、『ドラゴンクエスト』はその後、『ドラゴンクエスト2 悪霊の神々』『ドラゴンクエスト3 そして伝説へ』と続き、僕ら当時の子供たちの脳を焼きながらシリーズを続け、大人となった僕らをも魅了し続けている。
その意味では、子供心の『ドラゴンクエスト』と鳥山明氏のキャラクターデザインは、日本人のファンタジー観やRPG観を築いた源泉の一つと言っても、過言ではないだろう。その影響は、もはや潜在意識に刷り込まれており、抽出するのが難しいとすら言えるのではないか。
さて、僕らが生きてる現実には、教会も、ザオラルもザオリクも無い。死んだ人が生き返ることは無いのである。しかし、鳥山明氏が生み出した作品は、今、世界各国で生きている人々の心の中に生きているし、それに心動かされた人々が、更なる思い出や物語や作品を紡いでいくことになるのは確実だ。
様々な国の人々に楽しみを与え、人の心を動かし、新たな作品を生む原動力となったであろう鳥山明氏の業績は果てしない。
なまじな外交会議や経済支援よりも、鳥山明作品の方が、海外の人々の架け橋になっていることもあろう。また、人類への影響力として、後世、釈迦やソクラテスや孔子やキリストやムハンマドと並べて語られるのではなかろうか。なんて思ってみたりもする。
ともあれ、鳥山明先生の作品はもう見られない。それは確かに寂しいことには違いない。せめて、残された作品をきちんと愛することにしよう。どうか、安らかに。
.jpg) が
が
前の3件 | -



